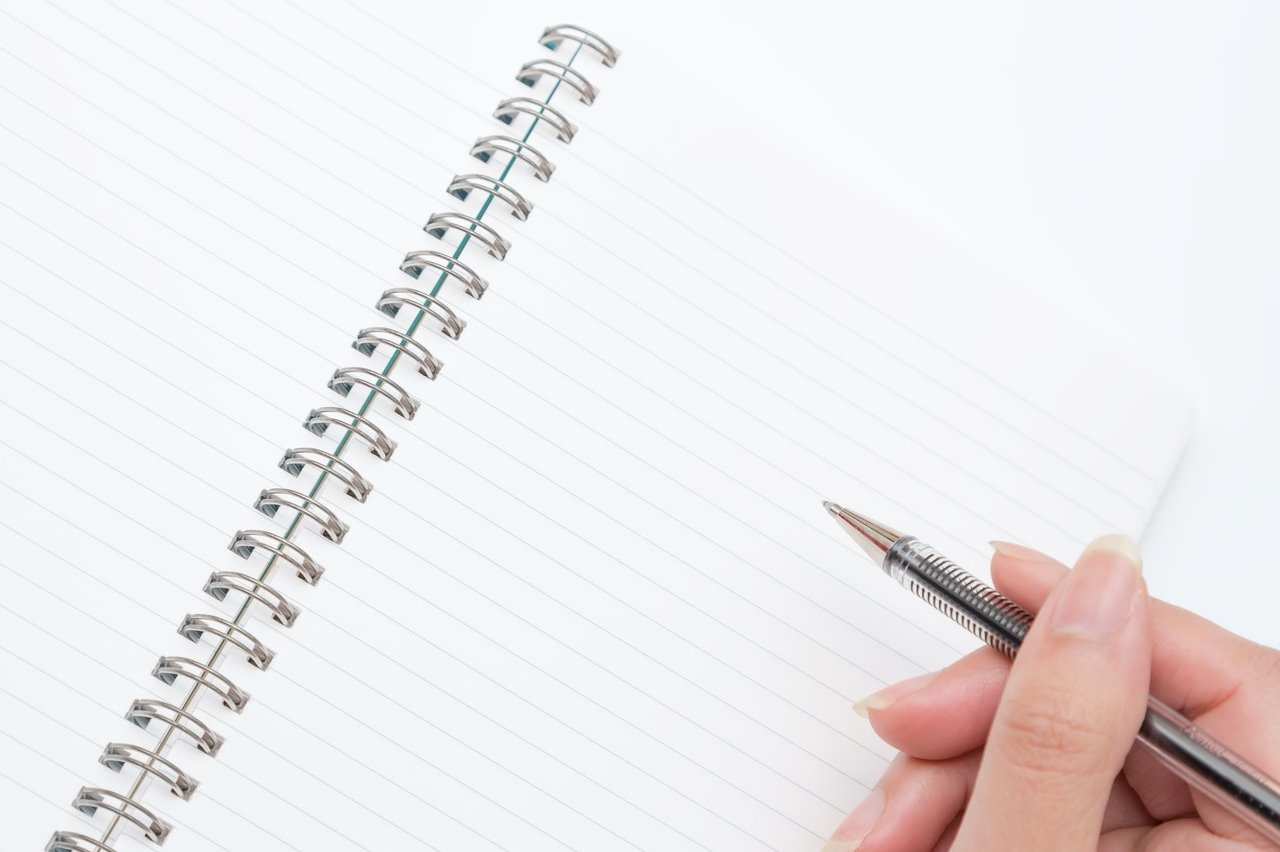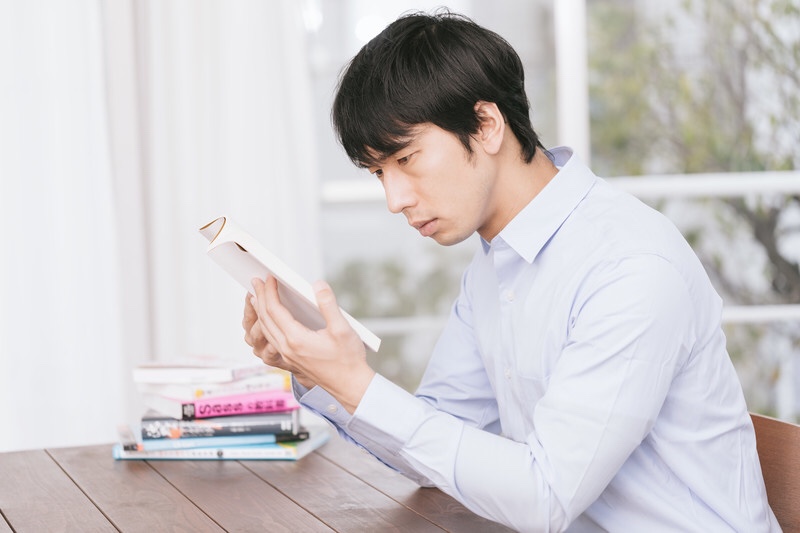家族が一人、二人と増えていく場合に考える必要があるのが扶養です。
よく、
「扶養に入っている」
という言葉を聞くと思いますが、働いていない配偶者や子どもは、
収入がないので、働く本人の収入内で扶養に入ることで、
健康保険を利用することが出来るようになります。
今回は、私学共済における子どもの扶養申請手続きについて見ていきます。
目次
子どもが扶養に入る場合
子どもを扶養に入れる際に行う手続きは、
「被扶養者認定申請」
と言います。
扶養に入ることが出来る人も限定されており、
「3親等以内の親族で、主として加入者に生計を維持されている人」
となっています。
子どもは当然収入がないので、加入者に生計を維持されている人に該当し、3親等以内の親族として被扶養者になることが出来ます。
なお、令和2年の4月より、国内居住要件が追加されたことにつき、
「日本国内に住所があること(住民票があること)」
も要件の一つとなりました。
これについては例外もありますが、詳細については今回は省略します。
上記手続きを行うことで、共済組合より、保険診療等をはじめとした日常生活における様々な給付を受けることができます。
そして、この申請手続きを行うにあたって、子どもが扶養に入る際には、以下のパターン分けをして考えていく必要があります。
①既に配偶者が被扶養者として加入している場合
子どもが産まれる前に、既に配偶者が被扶養者として加入している場合、
配偶者については既に扶養認定を受けているため、
確認書類に関しては子どもの書類と配偶者との関係性に関する提出だけで大丈夫です。
例えば、
・住民票
・戸籍謄本
・出生届受理証明書
などを添付書類として申請すれば良いということですね。
役所で取得する必要がありますが、子どもが産まれた際に出生届を提出する必要があるので、
届け出をした際に、あわせて上記の書類をいずれか取得しておけば良いでしょう。
もちろん、郵送でも取得手続きは可能です。
なお、現在、住民票や戸籍謄本等はマイナンバーカードによりコンビニ等でも簡単に取得出来るようになりました。
もし、取得し忘れた方でも、マイナンバーカードを取得していれば、
わざわざ役所に行かなくても取得することが出来るので、ぜひ、マイナンバーカードを所持している場合は有効活用して下さい。
マイナンバーカードに関する記事についてはこちらにまとめていますので、あわせてご覧下さいね↓
②配偶者が被扶養者ではないが、学校法人等からの扶養手当の受給がある場合
この場合も、配偶者以外の家族が既に扶養手当を受給していることにつき、
扶養認定を受けているということから、上記の①と同様の書類となります。
なお、配偶者が被扶養者ではないという場合は、例えば、ある程度働いて収入があり、
扶養の認定を受ける必要がない場合などがこれにあたりますね。
③本人と比較して配偶者の収入の方が多い場合
この場合、扶養認定の申請をすることが出来ません。
扶養の条件は、夫婦どちらかの年間収入が多い方に入る必要があるため、
配偶者の方の収入が多い場合、本人である私学共済加入者側で扶養に入ることは出来ず、
配偶者の勤め先の組合に申請する必要があります。
なお、本人の方が多い場合は、①の書類に加え、
「収入が多いことを証する書類(例えば、源泉徴収票の写しや所得証明書等)」
を提出する必要があるので、
その点もあわせて注意する必要があります。
このような収入に関する証明書類についても、例えば、源泉徴収票の写しが見当たらないといった
場合は、役所で所得証明書を取得することもできるため、
出生届と同時に、必要な書類はまとめて取得しておくと安心ですね。
被扶養者認定に関する申請期限について
扶養の申請をするにあたっては、申請期限があり、
「被扶養者の要件をそろえることとなった日から30日以内」
となっています。
この提出が30日を過ぎて遅れると、申請の届け出を受けた日が認定日となり、
さかのぼって扶養者になるということにはならないので注意が必要です。
つまり、もし遅れた場合、無保険期間が生じて、医療費を全額自己負担といったことも生じる可能性があるということなので、
そのような事態にならないように、速やかに事務員の方に提出しましょう!
まとめ
今回は、子どもが産まれた際における私学共済の扶養の申請手続きについて見ていきました。
扶養の認定を受ける場合は、上記のパターンに合わせながら申請する必要がありますが、
揃える書類自体は少ないので、特に難しい手続きというわけでもないです。
申請をするにあたっては、上記の複数の添付書類も必要となってくるので、出生届とあわせて必要な書類があれば、
まとめて取得しておくと、後々ラクになりますので、
届け出前に各申請についてはしっかり確認しておいて下さいね!
そのあたりは、学校にいる事務員さんにも相談しながら申請手続きをしていくと良いでしょう!