近年、労働時間の長期化により、教員が休職する問題が絶えません。
本当は元気に勤務継続することが一番ですが、使命感の高い職業柄であることもあり、真面目な先生程、休職を余儀なくされてしまいます。
そこで、休職した場合にはどのような生活保障になるのかについて、
- 病気休暇
- 病気休職
- 傷病手当金
という3つのカテゴリーに分けて下記まとめていきます。
特に、傷病手当金という名は一度は聞いたことがある方も多いと思いますが、どのような手当なのか、内容や条件が細かいこともあり、
具体的な部分まで分かっているという方は少ないかもしれません。
傷病手当金をもらう前の病気休暇や休職とセットで取り上げますので、これと併せてみていき、少しでも休職時の対応として参考にしもらえればと思います。
目次
まずは病気休暇・休職で対処!
まず、病気等による休職を余儀なくされた場合、
「病気休暇による手当」
があります。
いわゆる、「有給休暇」と同じですね。
病気等で休む場合、すぐ傷病手当金ということではなく、まずは病気休暇をもらって、それでも長期療養を余儀なくされる場合は傷病手当金を受給するという流れになります。
その病気休暇ですが、もらえる期間としては、最大90日間で、自治体によっては180日間という所もあるようです。
金額については、勤務していたころと同じ、
「全額支給」
となるため安心ですね。
病気休暇を過ぎた場合
病気休暇が過ぎた場合、今度は病気休職となります。
この病気休職期間は、最大1年間となります。
また、病気休職となると、もらえる金額については、
「給与の8割支給」
となるため、少し減額されるものの、生活を保障するうえでは十分な金額と言えますね。
この1年間を過ぎると無給となるため、公的保障制度にある傷病手当金の手続きに移っていくということになります。
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、共済組合に加入している組合員が公務以外により病気やケガをして、
それによる療養を余儀なくされた際、休業によって給与が減額されたときに、これを補填する形で、生活を保障するための給付のことを言います。
あくまで公務以外の場合のため、公務上発生した病気やケガを理由に休む場合は、公立教員の場合は労災ではなく、
別途地方公務員災害補償法による公務災害扱いになるため、そちらでの補償となります。
いつからもらえる?
支給はいつからはじまるのか?ということですが、これは
「病気やケガによる療養のために、引き続き勤務することが困難になった日から連続して3日を経過した日(勤務継続困難になった日から起算して4日目から)」
ということになります。
待期期間3日間について
注意点として、待期期間3日間という日数があります。
これは、仕事を3日間連続して休んでいなければならず、1日でも出勤してしまうと、傷病手当金に関する給付要件を満たさなくなるということです。
ただ、3日間連続して休むと給付要件が成立するので、例えば、3日間連続で休んだが、翌日出勤し、翌々日再度休んだという場合でも、傷病手当金は翌々日の日より手当の対象となります。
また、この待期期間は有給休暇や土日・祝日等も換算されるため、平日のみということではないんですね。
どの程度の期間もらえる?
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヶ月となります。
これは、あくまで支給期間の話であるため、1年6ヶ月分支給がされるということではないです。
例えば、1年6ヶ月の間に、身体の調子が良くて1週間程度出勤したものの、やはり続かず、再度休むということになった場合でも、出勤した期間については給与が支払われ、
かつ、その期間も1年6ヶ月の期間に含まれるため、再度延びるというわけではないということです。
附加金がある!
ただ、教員の場合は共済組合による附加金というものがあります。
色んな所で顔を出す附加金ですが、これがあることにより、さらに6ヶ月分の期間が足され、
教員は最長2年間給付を受けることができるということになります。
附加金については、私学共済についてもあるため、公立・私立問わず、教員は2年間の給付期間があるということですね。
金額はいくら?
金額については、以下の計算式、
「支給開始日に属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額×1/22」×2/3
があります。
これは、公立・私立問わず、同じ計算式となっています。
細かいですね。。
簡単なイメージとしては、一般的な会社員がもらえる傷病手当金は給与の3分の2になりますが、これより少し多いということですね。
普段もらっている給与からあまり減額されずにもらえるのはありがたい給付内容だと言えます。
もらえない場合もある!
もちろん、傷病手当金給付期間中に、別の報酬や手当金が発生するようなことがあればもらうことができません。
具体的には、
- 給料等の報酬
- 同一の傷病による障害厚生(共済)年金
- 障害手当金(一時金)
- 出産手当金
等が該当します。
上記を受給している場合は、傷病手当金を受け取ることができないので注意する必要があります。
最長3年半はなんとか生活保障がある!
以上、病気休暇や休職と傷病手当金の各内容について見ていきました。
これらの病気休暇や休職と傷病手当金の受給日数期間を合わせると、
病気休暇(3ヶ月間or半年間)+病気休職(1年間)+傷病手当金(2年間)
=(最長)3年半
ということで、
最長でも約3年半は生活保障を確保できるということになります。
いざというときでも、教員ならではの手厚い保障があるということが言えますね。
ただ、3年半以降は無給となり、それ以降も療養を余儀なくされる場合もあるかもしれません
そういった場合でも、それに対処するための教員向けの長期休業に備えた保険もあるので、心配な方はこれで備えておくのもいいです。
以前、その保険については下記の記事にまとめていますので、あわせてご覧ください↓
まとめ
今回は、傷病手当金を中心に見ていきました。
傷病手当金をもらうまでは、まず病気休暇や休職を利用して生活保障をし、それでも療養が続くようであれば、そこで初めて傷病手当金の手続きに入ります。
これらの期間を足すと、最長3年半は生活保障が確保できるということが分かるので、改めて手厚い保障があることが分かります。
一連の流れを事前に知っておけば、いざというときの対処もスムーズにいきますので、ぜひ上記の流れは押さえておいて下さいね!
下記のメルマガでも詳しくご説明しています↓






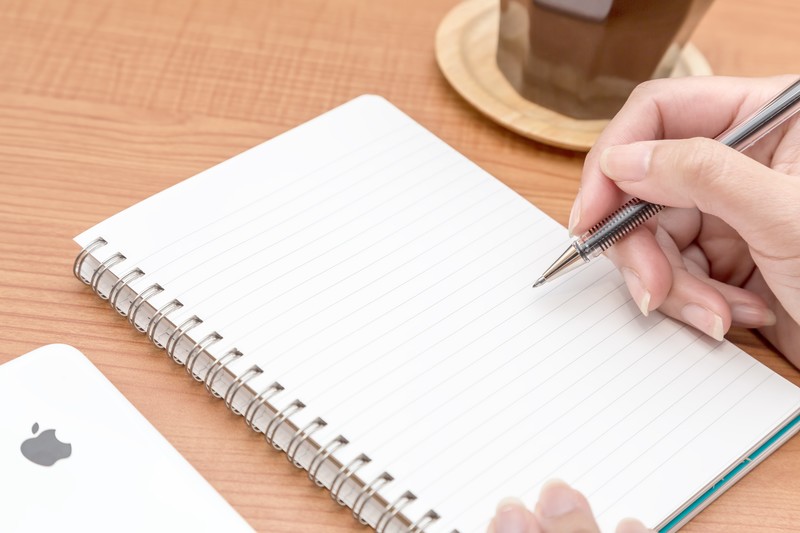



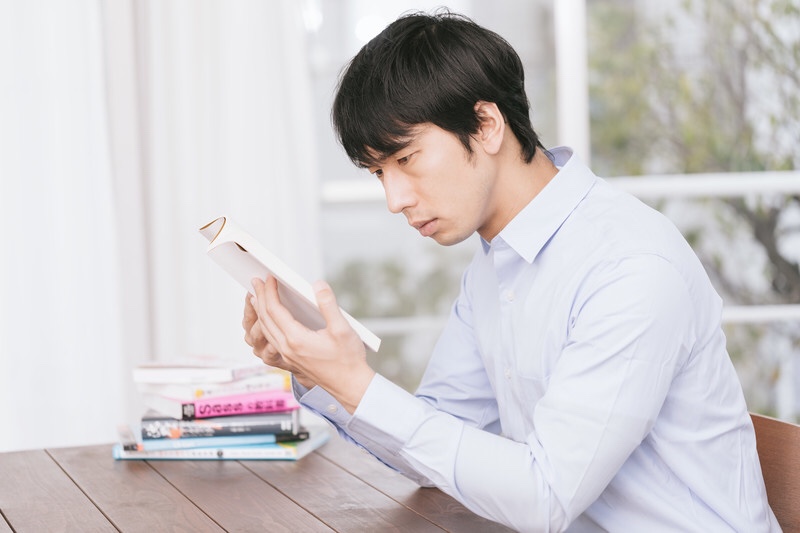
これは、講師も該当しますか?
すぎ様
FPの山下と申します。
コメント頂きましてありがとうございました。
記事についてですが、病休等の保障は基本的には正規教員が該当することとなります。
しかし、傷病手当金については健康保険組合に加入していれば受け取ることが出来ますので、
病休等と分けて考えて頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
怪我で休職するのですが、その後一度復職してから産休、育休を取得する事は可能でしょうか。同じ年度内で可能なのか、金額が変わったりするのか知りたいです。
田口様
FPの山下と申します。
コメント頂きましてありがとうございました。
ご質問についてですが、怪我による休職と育休や産休は制度として別であるため、復職後の取得も可能と言えます。
また、同年度内でも取得は可能ですが、産休前に休職する場合は育児休業手当金の計算が休業開始前の賃金を基に計算を行うため、場合によっては減額等の可能性があることは考慮した方がよいですね。
以上になりますが、ご参考にして頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。