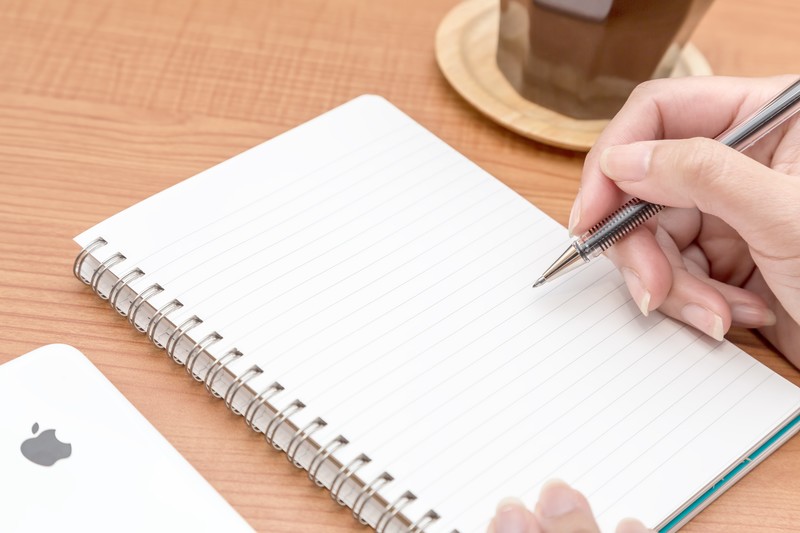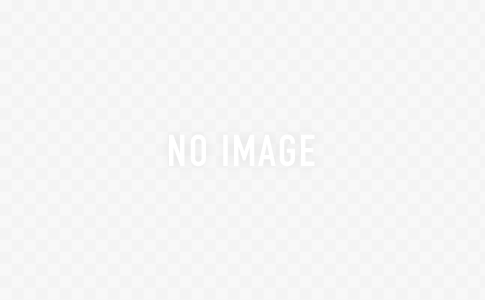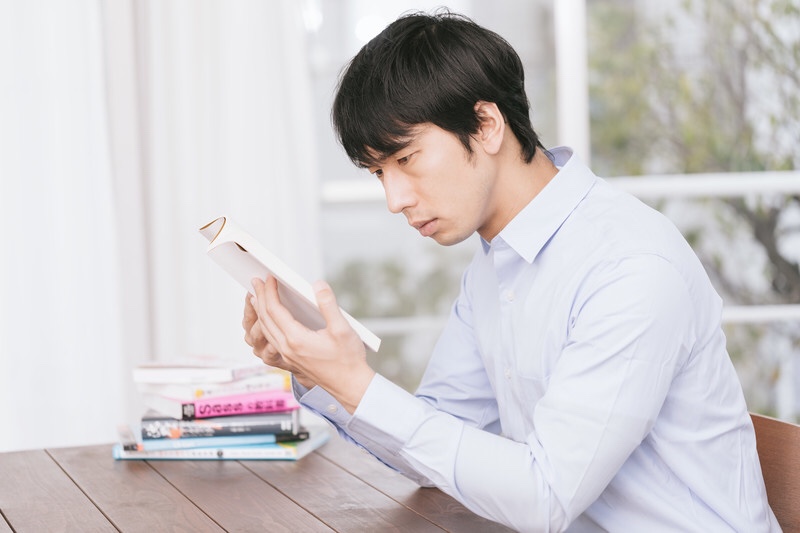教員の身近にある団体保険を知っていますか?
保険には一般の保険と、職場ごとにある団体保険があります。
どちらがいいのかという点もそうですが、そもそもどのような違いがあるのでしょうか?
教員は団体保険を優先して検討することで、家計における保険支出の負担軽減にもつながっていきます。
今回は、教員が検討すべき団体保険について詳しく見ていきます。
目次
団体保険とは?
団体保険とは、所属する会社や団体が、グループとして提供している保険の事です。
一般的な保険は、団体保険ではなく、それぞれの保険会社が独自の商品として提供しているものであり、保険料も決して安くないです。
対して、団体保険はその団体の代表者が契約者になり、そこに所属する人たちが被保険者としてかけるものを言います。
ですので、当然、その団体に所属していないと加入することができないということですね。
もちろん、その家族であれば加入対象者になっていることも多いので、家族全員で同じ団体保険に加入することも全く問題ありせん。
教員で言えば、教職員共済も団体保険の1つですし、日本教育公務員弘済会が提供している保険も団体保険の1つです。
団体保険に加入するメリットについて
では、加入する際のメリットはなんでしょうか?
加入メリットの一つ目
まず1つ目として、保険料が安いということです。
一般的な保険料と比較して、割引率が高く、必要以上に保障額も大きくない事から、相対的に安くなります。
また、告知もそこまで厳しくないということも利点ですね。
保険は、どうしても告知で引っかかって入ることが出来ないというリスクがありますが、
団体保険は、比較的、告知制約が緩いので、保険に加入しやすいという側面があります。
こういったときに、前に既往歴があったり、手術した過去などがあると、入れなかった保険も入ることが出来るようになるという状況にもなり得るので、やはり、加入のしやすさは大きなメリットとなるでしょう。
加入メリットの二つ目
メリットの2つ目は、現在、個別に民間の保険に入っている方も、団体保険に切り替えることが出来るという事ですね。
まず、団体保険扱いにすることで、メリットの一つ目にもあげましたが、保険料が割引きになります。
しかも保険料控除の手続きも互助会等が行ってくれるので、保険料の控除証明書を用いて年末調整の提出を自身でする必要もなくなります。
これは、給与から保険料が自動で天引きされるので、自身でする事がなくなるということなんですね。
ただし、保険商品や都道府県によって違いが出てくるため、全てが同じような取り扱いとはならないことから、その辺りは確認してみて下さい。
加入のおけるデメリットについて
団体保険に加入する際のデメリットについては二点ほどあります。
以下、あげていきます。
加入デメリットの一つ目
まず、1つのデメリットとして、
「会社を退社した際には継続ができなくなる」
ということです。
例えば、教職員共済については、各商品によって退職後の取り扱いが異なります↓
一生もので考えていた保険なのに、辞めざるを得なくなると、改めて保険の見直しをしないといけないので、少し面倒な部分は出てきます。
種類によっては継続出来るものもありますが、その点については、加入時にしっかり確認しておく必要があるでしょう。
加入デメリットの二つ目
二つ目のデメリットについては、
「共済保険では保障額の上限額が低くなりやすい」
という点です。
教員の団体保険には、民間の保険以外に共済保険も多いです。
例えば、生命共済について加入を検討している場合、共済保険は割安であるということもあり、保障額の上限額も低額になりやすいという側面もあります。
大きな保障額を確保する必要がある世帯については、その辺りを注意する必要があるということですね。
団体保険と民間の保険は結局どちらがいい?
実は、保険の入り方は基本的に二者択一とかそういう判断ではないんですね。
生命保険などは特に、
「必要保障額」
に基づいた選び方が大事になってきます。
例えば、教員で言えば、ベースを団体保険に据え置きながら、他の民間保険を考えていく方が選びやすいでしょう。
また、弘済会の保険についても、その他の民間の医療保険では取り扱ってない保険なども取り扱っています。
そうすると、選択肢の幅が広がり、他から保険のお誘いが来ても、団体保険を優先して考えることで、勧められるがままに保険に加入するという状況は生まれないでしょう。
なぜなら、団体保険という選択肢があることを知っているだけで検討材料になりますし、他との比較も出来るので、安易に加入するような状況にはなりにくいからなんですね。
それほど、やはり勧められたまま保険に入るのは、保険料の無駄につながってしまうリスクが懸念されます。
必要保障額さえ知っていれば、後は商品の選定に苦労せず、見直しをする機会にも役立っていくということですね。
まとめ
今回は、団体保険について取り上げてみました。
保険は、一般的な保険だけではなく、このように所属している団体が設けている保険もあります。
大概は安かったり、保障内容は充実してないけど入りやすかったりなど、人によってはありがたい側面もあります。
しかし、相対的に保障額が低い事もあり、特に子どもがいらっしゃる世帯は、安易に検討して加入することがないように注意しなければなりません。
その辺りは、必要保障額を保険会社のHP等から簡単なシミュレーションをしてみて、まずはしっかり算出してみることが大事ということですね。
そうすると、より保険を選びやすくなり、団体保険のコスパの良さにもだんだんと気付いてくることでしょう。